前回記事の復習
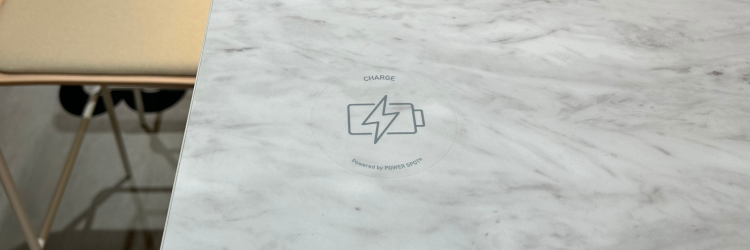
「仲間を見つける、想いをつなげる」がテーマのNEWVOT³の3階。
オフィスでも気軽な会話ができるようにと設置されたバーカウンターの天板にはワイヤレス給電が設置されています。
「電源」と聞くと、少し堅いイメージを持つかもしれません。でも、スマートフォンや家電、オフィスの照明まで、私たちの暮らしは電力なしでは成り立ちません。
そんな“当たり前”を、もっと自由に、もっとスマートに変えていこうとしている企業があります。
2019年に誕生したスタートアップ「ベルデザイン」は、産業機器向け電源メーカーとして長い歴史を持つ「ベルニクス」を母体に、ワイヤレス給電という新しい技術に挑戦しています。
”ケーブルのない世界”を目指して、技術だけでなく、環境や社会への想いも込めて事業を展開するベルデザイン。
今回は、そんな彼らの取り組みと、未来に向けたビジョンについてお話を伺いました。

今回のインタビューのお相手は、、、
株式会社ベルデザイン
代表取締役CEO 鈴木様(以下敬称略)
VENICHU MAGAZINE編集部(以下、VM):ベルデザインとはどのような会社か教えてください。
鈴木:ベルデザインは2019年に設立したスタートアップ企業です。
元はベルニクスという創業48年目の会社で産業機器向けの電源メーカー(電車・新幹線・医療機器・携帯基地局等)です。電源をお客様や業界の規格に合わせて電源を作っています。
VM:ありがとうございます。
早速ワイヤレス給電についてお聞きしていきたいのですが、私の中ではワイヤレス給電が身近に普及したのはここ数年の気がしています。産業機器の業界ではワイヤレス給電はもっと前から使用されていたのでしょうか
鈴木:たしかにあまり身近ではないかもしれませんが、産業機器には多く使われています。
そもそも多分電源ってもの自体意識しないで取り敢えずコンセント挿さなきゃいけないから挿すって感覚だと思うんです。例えば、パソコンと冷蔵庫も同じコンセントに同じ形のものを挿すので、意識してないと思うんですけど、全部中に入っている電源自体は違うものなんですよ。
まさに元々電源って意識されない中で使っていたところに、ワイレス給電が生まれて今までと全く違う用途で電源が使えるし挿さなくていいという新しい給電の形ができました。
VM:どのような場所にワイヤレス給電が使われているのでしょうか。
鈴木:産業機器の中では、医療機器だと内視鏡とか、運送装置(荷物を運ぶもの)とか、線が交差して断線したら困るようなところに使われています。
線って被膜がめくれてコードが出てそれを触ってしまうと感電してしまうじゃないですか。なので水回りとかコードがあるものは危ないのでそういう場所で使われることが多いですね。
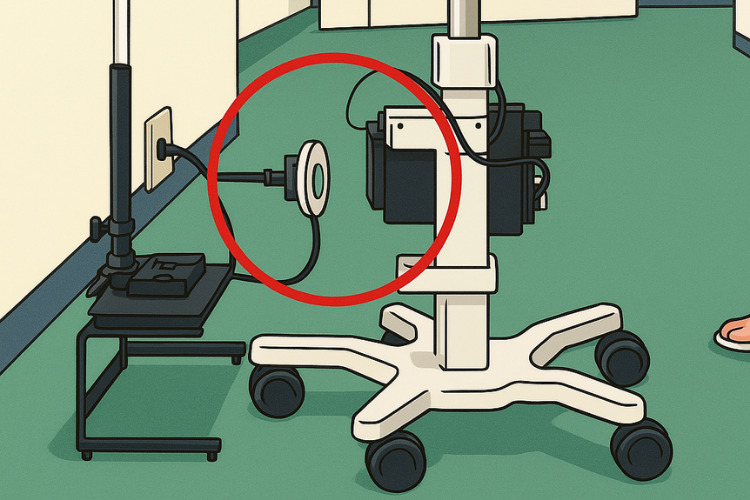
医療機器のワイヤレス給電(イメージ)
VM:産業機器業界から、一般的な場所でワイヤレス給電を普及させようと思ったきっかけを教えてください。
鈴木:産業機器では当たり前に使われいて、ワイヤードと比べると便利な場所がいっぱいあって、いちいちケーブル繋がなくていいとか、水に濡れても大丈夫だとかそういうメリットがあるのになんでこう広がってかないのかなみたいな疑問がずっとありました。
そこでベルニクス側の大手の取引先様にワイヤレス給電のプラットフォーム構築しませんかってお声がけをしたんですよね。
でも、「100年近く変わらない電気の配り方を変えていくのは難しいよ」って皆に言われました。
まあ新しいことを始めようと思ったら、誰が最初にやるのか、他の会社はどうするのか、ってなるのは仕方ないことではありますけどね(笑)
VM:たしかに。新しいことを始めるということには大きな労力が必要ですよね。
鈴木:はい。その時に思ったのが技術は自分たちで持っているのに、使ってくれるお客様がいないまま、何もしないでいると、気づいたらアメリカで流行り始めて、、、
そのあと、韓国や中国、台湾が製品をどんどん作って、結局それを日本に持ってくる、みたいな状況になってしまうんじゃないかって、ちょっと感じたんですよね。
今までの技術発展の流れの中で、そのパターンを見てきましたがなんとなくモヤモヤしていたんです。
なのでいっそのこと、自分たちでその未知の領域に挑戦してみようって思ったんです。
VM:では、そこからベルデザインとしての挑戦が始まったんですね。
鈴木:そうですね。老舗のベルニクスって看板にはすでに色があったので、新しいプラットフォームを作っていくにはスタートアップでまっさらな状態で会社を作って、共感する人達と一緒に町や駅、家、車の中にどんどん普及していこうと思って作ったのがベルデザインなんです。

VM:前回記事でワイヤレス給電のIOT化についてもお聞きしましたが、その使用方法や技術の広め方、認知についてはどのようにお考えでしょうか。
鈴木:電気って、目に見えないし色もないから、どんな電力を使っているかなんて普段は意識しませんよね。ベルデザインが開発するワイヤレス充電スポットは、IOT技術を使ってそんな“見えない電力”を“見える化”することができないかと考えています。
VM:現状どのような課題があるのでしょうか。
鈴木:まず前提として、再生可能エネルギー(以下再エネ)の導入・活用が日本のエネルギー問題の課題にあるので太陽光発電などを使用して取り入れるビルの建設も増えてきています。
例えば、ビルを新しく建てて再エネを利用しているとしても、ユーザーがそれを“体感”できなければ、行動変容にはつながりません。通常はユーザー側からしたらただいつも通りコンセントから流れてくる電気を使用しているという感覚しかないですからね。
「電気には色がない」。これは、再エネの普及において、非常に本質的な課題だと考えています。
VM:では、その課題を解決する電力の”見える化”のイメージを教えてください。
鈴木:具体的には、充電スポットに組み込まれたセンサーが使用電力をワット単位で測定し、再エネ由来の電力かどうかを判別します。POWER SPOT®を専用アプリと連携することで、ユーザーは「今、自分が使っている電力が再エネである」ことを確認できる仕組みです。
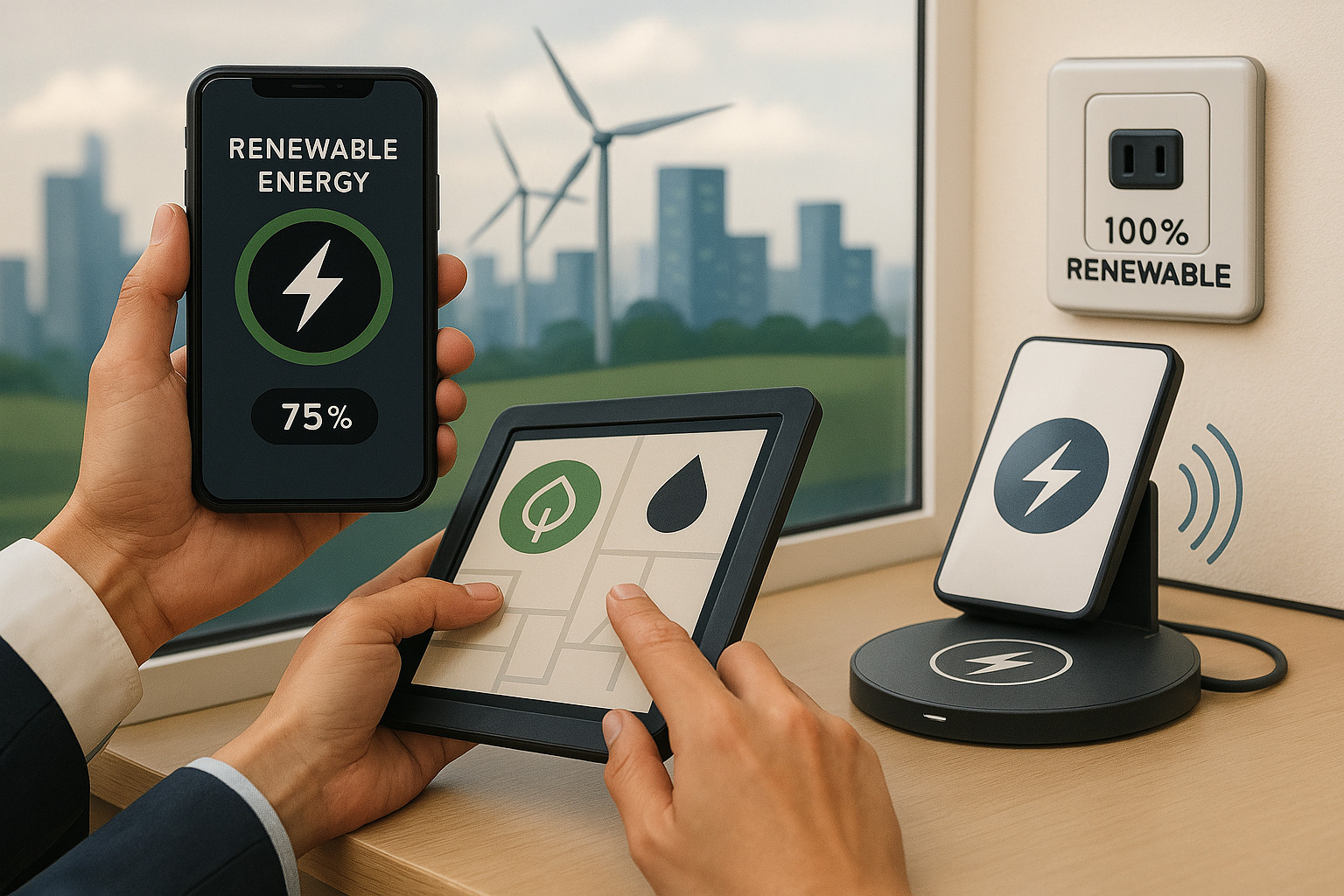
自分が使用している電気がどこからきたのかがわかる未来
VM:なるほど。アプリで見れるようになったらわかりやすく面白いですね。
鈴木:まだ構想段階ではありますが、再エネ利用に応じてポイントが付与され、カフェやECサイトなどで割引などの社会的対価として還元される設計にしたいと考えています。これは、環境価値を経済価値に変換する新しいモデルであり、SDGsの「つくる責任・つかう責任」や「気候変動への具体的な対策」にも直結する取り組みです。
VM:「便利なだけじゃなく、環境にも良い。そして、ちょっと得する」とても素敵な体験ができそうですね!
鈴木:はい。そんな体験を通じて、ユーザーが知らないうちに脱炭素社会に貢献できる。私たちは、ワイヤレス給電という技術を通じて、社会と個人の意識をつなぐプラットフォームを構築しようとしています。
VM:今回のお話を聞いて、あらゆる場面でワイヤレス給電が利用できそうだなと感じています。
POWER SPOT®を広めていくなかで今後挑戦したいことはありますか。
鈴木:いろいろ考えていますよ。例えば、オフィスの床下に送電ユニットを埋め込むことで、レイアウト変更時の電源工事が不要になり、柔軟な空間設計が可能になると思います。
他にも、ソファやテーブルなどの家具に充電機能を組み込むことで、ケーブルレスな生活環境を実現したいですね。火災リスクの低減や空間効率の向上にもつながるのではと考えています。
VM:確かにコンセントに”挿す”という行為が減り、”置く””乗せる”だけでいいと思うとかなり生活がラクになるかもしれませんね。
鈴木:はい。今後は送電距離の拡大や、充電可能な厚みの向上(現在約1cm → 将来的には3cm)を目指しており、今より分厚い木材や大理石などの素材にも対応できるよう技術開発を進めています。
家庭だけでなく、駅や学校などの公共施設、さらには物流ロボットや警備ロボットなどの自律機器への応用も視野に入れており、都市全体をワイヤレス給電で支えるインフラへと進化させる構想です。
VM:近い将来にはワイヤレス給電が当たり前になっていると面白いですね。
鈴木:「電源を“探す”のではなく、“空間が電源になる”世界へ」
そんな未来を現実にするために、ベルデザインは技術と社会の接点を広げ続けています。

見えない電気で、暮らしを変える。ベルデザインは、ワイヤレス給電の力で、環境にやさしく、便利で快適な未来を目指しています。
ワイヤレス給電で暮らしがアップデートされる未来が楽しみです!
POWER SPOT®はNEWVOT³の3階でご利用いただけますので、ぜひご利用ください。
取材協力
紹介商品

