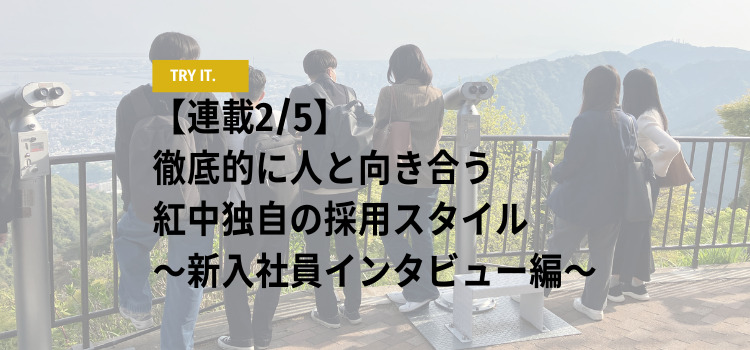
前回は今年の新入社員へのインタビュー記事をお届けしました。
今回は、内定後から入社までの期間に実施される研修やイベント、フォロー体制について、人事課課長のCさんへ取材をおこないました!採用改革による「攻める採用スタイル」への変化の過程や、学生に対する想いなど、様々な角度からお話しを聞いてみました。
VENICHU MAGAZINE編集部(以下、VM):最長でどのくらいの期間、内定者フォローをおこなっていますか?
Cさん:早いタイミングの学生だと3年生の1、2月には内定が出ているので、翌年4月入社までの約14か月間フォローをおこなうことになります。
内定が出るタイミングが人によってバラバラなので、早期に内定が出た学生には、期間が空いて不安にならない程度に定期的に連絡を取りつつ、ある程度内定者が揃う時期である4年生の6月頃に、内定者同士の顔合わせをおこなっています。
そして、内定者が予定人数に達する8月から、半年間(月に一回)の内定者研修をおこない、社会人に向けた準備をスタートさせます。
VM:早くに内定が出た学生だと、研修が始まるまでにも半年期間が空くことになるんですね。その間のフォローである連絡というのは、どういったことを主にされているんですか?
Cさん:2か月に一度程度、最近どうですか?というようなメールでの簡単な連絡であったり、最近の紅中の状況や、他の内定者がどれくらい集まっているかなどを電話でお話しするようにしています。
連絡頻度が多すぎても煩わしく感じるだろうし、少なすぎると放っておかれている感覚にさせてしまうので、いい塩梅が難しいところではあります。
VM:入社までに実施されている研修やイベント、その他フォロー内容について教えてください。
Cさん:先ほどの内容と一部重複しますが、6月にまず内定者交流会をおこなっています。このタイミングが、内定者複数人で集まる顔合わせとしては初回になります。
8~1月の半年間が内定者研修で、WEB形式と対面と織り交ぜて実施しています。研修自体は月に一回ペースではありますが、内定者全員で進める課題があるので、この間内定者同士は常々連絡を取り合っていますね。
VM:毎回研修の度に課題が出ると聞きました!結構ハードですよね。
Cさん:そうですね(笑)研修以外の時間にも、自主的に打合せをしないと達成できないような課題内容になっています。ただ、この期間が同期との仲を深める機会となればという思いで、こちらとしては取り組んでいます。
研修の中盤に差し掛かった10月には内定式をおこない、このメンバーで春から頑張っていこうと改めて気持ちを引き締めてもらいます。そして研修終了後、3月に入社前の最終準備として入社前面談を実施しています。

VM:それらの中でも、「これは紅中ならでは」と言えるようなフォロー内容はありますか?
Cさん:正直、ならではと言えるほどのことはまだないのですが…
そもそも、今のようにフォロー期間が長くなったのも、採用改革が始まった25卒からなんですよね。外部のコンサルティング会社に伴走してもらい、プロの知恵を借りつつ、紅中の新しい採用スタイルを作ってきました。
それ以前まではこのような体制ではなく、通年ずっと採用活動をしていたので、早期内定者の場合でも長くて半年程度のフォロー期間だったんです。それが急激に前倒しになったので、私たちもできるところからやっているという感じではあるんですが、とにかく入社までに期間が空くというのは学生側が不安を抱いてしまうことは理解しているので、そこを払拭するためにこまめに連絡を取るようには心掛けてきましたね。こちらとしても同じように不安な面はあるので。
VM:改革はやはり大変なことも多かったですか?
Cさん:大変なことばかりでした(笑)
私が入社して採用担当になった頃やそれ以前は就職ナビサイトも使わず、合同説明会に直接出向き、そこで縁のあった学生の中から選考を進めるという手法を取っていました。会える学生の母数も少なければ、興味を示しブースに訪れてくれる学生にしかアピールができない。言わば受け身のスタイルだったんですよね。
そこから新卒採用サイトなどのコンテンツ作りや、趣向を凝らしたインターンシップなど、こちらから学生側にアプローチできる機会を増やし、今は攻める採用スタイルに変化しています。
VM:内定者から、この研修は好評だったなどの声をもらったことがあれば教えてください。
Cさん:研修期間中、毎月課題が出るのはやはり学生にとって負担なのではと思い、講義を受けるだけの形式はどうか?と今の採用方式を受けて入社したメンバーに聞いたところ、「大変だったけど、あの時間があったから社会人としての心の準備ができた」という理由で必要という意見が多く返ってきました。これは私としても嬉しい声でしたね。
また、「入社前に同期とやり取りが増えることで、同期に対する不安は全くなくなった」「相談できる人ができて安心につながった」という声も。少なからず研修よりも遊びたいと思うので、研修を実施すること自体が好評なのかは分かりませんが(笑)

VM:毎年、内定承諾後~入社までに辞退を申し出る学生も一定数は発生しますか?
Cさん:やはり一定数は発生しますね。選考前から長くやり取りをする方がほとんどなので、辞退はとても悲しく思います。
ただ、数回設けている面談の時点で、辞退者となり得る方からは選考に進むか迷っているという旨はヒアリングできることが多いので、そこはある程度の関係性は築けている証拠だとも感じています。選考や面談の際は本音で話すことを大切にしているので、辞退の理由も皆さんしっかり伝えてくれますし、辞退者の方が真剣に考えて出した答えを応援したいと思っています。
VM:まさにタイトルのとおり”徹底的に人と向き合う”を体現されているんですね!
Cさん:そうですね。一人一人とじっくり向き合うことは常に大事にしています。
あとこれは余談なんですが…最近多いのが、希望業界は別にある中で、紅中を候補に残してくれるパターン。例えば、IT業界中心に他社の選考は受けているけど、その中に紅中が選択肢として残っている、というような。紅中という会社自体に魅力を感じて選考に進んでくれているのは嬉しいですね。
VM:選考の時点で会社に愛着を持ってくれているのは嬉しいですよね。お話し前後しますが、内定辞退に関してはどのような課題を感じていますか?
Cさん:前述のとおり採用の早期化が進んでいるがゆえに、学生も就職先を決めきれず、その結果内定辞退につながってしまうことは理解しています。この現況を課題として感じていますね。
VM:現状のフォロー体制全般についてどう感じていますか?良いと思っている点、変えていきたい点などあれば教えてください。
Cさん:良い点としては、内定期間に社会人の基礎の基礎ではあるものの学ぶ機会を与えることで、学生気分のまま社会人生活がスタートしないように助走期間を設けることができていることですね。また、内定者研修の期間中に同期同士の横の繋がりを作ってくれるので、4月の入社式や研修がスタートした段階から楽しそうにしている姿を見ると嬉しくなります。
今後変えていきたい点としては、内定の出る時期がバラつくことにより、経験させてあげられる内容が人によって異なることに対して、何かしら対応を取っていきたいと考えています。長いと半年以上差が出たりするので、平等性に欠けるのが問題だと感じています。
例えば、説明会に参加後、次のステップの日程が合わずに選考に進む機会を失ってしまった…というような課題にも対応できるよう、順次新しい日程が組まれたら案内を送るようにしています。
案内メールは単に選考プログラムの日程案内だけでなく、説明会で話すまでではない紅中のプチ情報や、福利厚生、社員の服装など、”調べれば出てくるけど、なかなかそこまで調べない情報”をメルマガ的に配信しています!
今回は内定者のフォロー体制にフォーカスを当ててお届けしました。
誰一人として取りこぼさず、真摯に一人一人と向き合っていることがよくわかりました。
次回の連載第4回では、入社後に実施している新人研修について詳しくご紹介します!座学だけではない、紅中ならではのプログラムが盛り沢山ですよ◎

